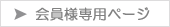
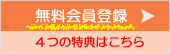
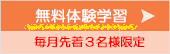
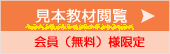
|
|

受験する大学の試験科目に小論文がある場合、どうしても知っておくべきことがあります。
それは・・・
「採点基準」です。
採点基準を知らなくても、ただ文章を書く練習をしていればよいのでしょうか?
採点基準を知らなくても、どこかで添削講座を受けていればよいのでしょうか?
それでは、非常に不安だと思います。
「わたしの小論文は、採点官からどんな評価をされるのかしら?」
「ぼくの小論文は、いったい何点くらいの評価なんだろうか?」
このような不安を感じるのは当然のことだと思います。
たとえば、「近代化と西洋化の関係について、あなたの意見を自由に述べなさい。」というテーマが出題されたとします。
「よし、しっかり自分の意見を書けたぞ!」
いくら自分自身がこのように感じても、採点官からどう評価をされているのか分かりません。
ほとんどの大学では、採点基準を公開していません。
知りたくてもなかなか知ることができないのが現状なのです。
「じゃあ、どうすればいいの?」
このように思われることでしょう。
お気持ちは分かります。
でも全く心配はいりません。
なぜならば、作文小論文専門学院は、採点官による採点基準を把握しているからです。
どうしてでしょうか?それは・・・
「採点官」の方から基準を説明していただいたことがあるのです。
当学院では、その採点基準を基本とし、「8項目」の基準を設定しています。
8項目について、「A・B・C・D・E」の5段階評価を導入しています。
5段階の意味については、下記の通りです。
A):非常に優秀
B):優秀
C):普通
D):やや弱い
E):弱い
8つの項目に細かく分けていますので、どこが改善ポイントか、どこが素晴らしいのか良く分かります。
「ここが弱いんだな。だったらそこを改善しよう。」という意識をもてばいいのです。それが合格への近道といえるでしょう。
8項目をそれぞれ5段階評価にしていますので、それぞれがどの程度できているのか良く分かります。
※総合評価も設けています。(総合評価も5段階評価)
総合評価が、「A判定」になりますと、合格レベルに到達しているといえます。
【総合評価】
総合A判定):合格率80%以上
総合B判定):合格率65%以上80%未満
総合C判定):合格率50%以上65%未満
総合D判定):合格率35%以上50%未満
総合E判定):合格率35%未満
注):総合判定はバロメーター(目安)であることをご理解ください。
※高校1・2年生においても、大学合格を意識してほしいので、3年生と同じように、A・B・C・D・Eの総合判定も導入しています。将来の合格の目安にし、励みにしてもらえればと思います。 |
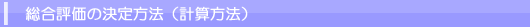
総合評価の決め方(計算方法)を説明しておきますね。
8項目それぞれの5段階評価(A〜E)を下記の点数として計算し、総合評価を決定します。
A)・・・4点
B)・・・3点
C)・・・2点
D)・・・1点
E)・・・0点
≪総合A判定≫
合計点数が、30点以上で「A」と評価されます。
注):ただし、8項目中1項目でもC以下(Cを含む)があると、A判定とはなりません。
≪総合B判定≫
合計点数が、26点以上で「B」と評価されます。
注):ただし、8項目中1項目でもD以下(Dを含む)があると、B判定とはなりません。
※8項目すべてBの場合は、合計24点となり26点未満ですがB判定となります。
≪総合C判定≫
合計点数が、18点以上で「C」と評価されます。
注):ただし、8項目中1項目でもEがあると、C判定とはなりません。
※8項目すべてCの場合は、合計16点となり18点未満ですがC判定となります。
≪総合D判定≫
合計点数が、10点以上で「D」と評価されます。
注):ただし、8項目中3項目以上Eがあると、D判定とはなりません。
※8項目すべてDの場合は、合計8点となり10点未満ですがD判定となります。
≪総合E判定≫
合計点数が、9点以下だと「E」と評価されます。 |
 

|

